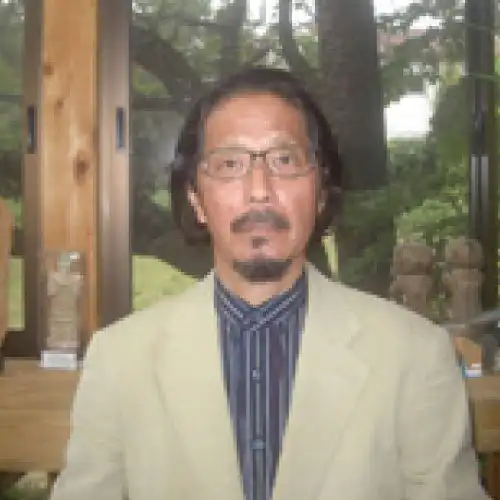第三者意見
J-オイルミルズレポート2025を読んで
わが国の2024年版の統合報告書発行企業は初めて1100社を超え、東証プライム上場企業でみると発行企業の時価総額は全体の90%を占めています。このように増大したのは、統合報告書の発行を契機に社内のサイロが打破され各部門間の対話が活性化された結果、企業行動が変化して企業価値の向上や社会課題の解決が促進されるからではないでしょうか。このことから優れた統合報告書は、企業内外の情報の棚卸や各ガイドラインの適応だけではなく、企業ビジョンの実現や価値創造への熱い意志と取り組む姿を社会に示す「将来社会に向けた存在意義証明書」であるべきと考えます。
本報告書はこうした優れた統合報告書に向けて不断の努力を重ねた成果です。この間、私は第三者意見を提出するだけでなく、社長、役員の参加された意見交換会、コメントの提出などを行ってきました。本年もコメント(1.価値創造ストーリーの解像度向上、2.情報の非対称性に配慮した開示、3.マテリアリティの深化、4.財務と非財務の関係性の可視化、5.DXのロードマップ提示)に対し、改善に向けた具体的な対応と残された課題を示されました。改善はこれまでに比べ飛躍と呼べるほど大きな変化が見て取れ、コメンテーターとして身が引き締まる思いです。
しかしながら、統合報告書の完成形はありません。経営環境は常に変化し、持続的な価値創造を行っていくためには、統合報告書には欠かせないマテリアリティや価値創造プロセスを常に見直すことが求められています。そのためには、これらの抽象的な概念に対し考え抜く力を発揮し、具体的な事項に落とし込むことが必要です。そして、その成果を外部のステークホルダーに提示するとともに、組織の一人ひとりが統合報告書を徹底的に活用して、日々の業務における自己認識を深めることが重要と考えます。
改善点で特に評価したいのは価値創造ストーリーの解像度向上とマテリアリティの深化、です。2024年版の価値創造モデルは「国際統合報告フレームワーク」のいわゆるオクトパスモデルに項目を提示しただけで具体的なストーリーの把握はできませんでした。本年版は各項目に関連ページが記載され、そこには具体的な施策やデータがあり、価値創造に向けての各項目の位置付け、内容が分かるようになりました。PBR逆ツリー展開においてもサステナビリティ経営の推進・強化や情報開示の促進・強化などのESG事項が具体的に示されました。また、ダブルマテリアリティの視点でモデルの中にインパクトが表示されました。これは、「事業が環境や社会に対してどのような影響を及ぼしているのか」というインパクトへの開示要請が高まっていることへの対応と考えます。ただ、その内容が関連ページの記載もないのでわかりません。ぜひ、マテリアリティの箇所でインパクト(ポジティブ・ネガティブの両方)の内容を明らかにしてください。
価値創造ストーリーは統合報告書の肝ですので、その解像度向上に向けた取り組みは絶え間ない課題です。今後、モデルに加えて資本別の価値創造パスや企業価値創造のロジックツリーなどを作成されると解像度の向上に寄与するのではないでしょうか。
マテリアリティの深化については、ESGや事業基盤強化に関する施策を4つのマテリアリティと関連付け、2030年のゴールイメージと2024年度の実績を記載することによって事業環境と戦略、施策をマテリアリティと接続させた事があげられます。マテリアリティをこのように整理することによって、投資家をはじめとするステークホルダーに対しマテリアリティを経営の核とする姿勢と取り組みを具体的に伝えることができます。また、従業員に対しても、日々の取り組みがどのマテリアリティに該当するかが分かり、マテリアリティ浸透に大きく影響するでしょう。
さらなる深化に向けて、前述したようにマテリアリティの枠組みに沿ってインパクトを丁寧に説明することです。一部に逆風がありますが、企業の社会的責任に関する関心は高く、インパクトが中長期的に財務的影響を及ぼすことは資本市場において共通認識となっています。
将来展望を大きく切り開くものとして印象に残ったのは、「人財ポリシー」を定め経営会議の諮問機関として「人財委員会」を設置し、人的資本経営の推進を明確にしたことです。貴社はこの間「復活と成長」を果たすために構造改革に取り組んでこられ、現在は次のステージ「成長」に入ってきました。人材版伊藤レポートでは「企業の直面している経営上の課題は人材面における課題と密接に関連している」と指摘しており、人的資本経営に大きく舵を切ったことは賢明な選択といえましょう。
次年度以降、人的資本経営の進捗の報告に期待しますが、その際の大事な視点は「経営戦略と人材戦略の連動」です。この点については人材版伊藤レポートをはじめ本報告書においてもCHROや池田取締役の発言をはじめ随所に連動の重要性が述べられています。こうした視点に立った開示=人的資本経営の可視化は自社の抱える課題を明確に把握することができると確信しています。
最後に「長期経営戦略の構築」を期待します。最近のアンケート調査によると、長期経営戦略の必要性を感じている企業は増加し、全体の80%以上にのぼっていますが現状では構築している企業は36%に過ぎません。VUCAの時代といわれる今日、確かに将来の経営環境を見通すことは困難になってきています。とはいえ、ビジョンを実現するためには変化の後追いではなく主体的な変化への先取り、すなわち長期経営戦略の構築が必要なのではないでしょうか。CEOも「長期的な成長戦略が描けないことのリスクは以前より増しています」とおしゃっています。構造改革を重ね成長のステージの立った現在、そして2027年から始まる第7期中計の策定を目前にした現在、長期経営戦略を構築する時ではないでしょうか。